逆流性食道炎
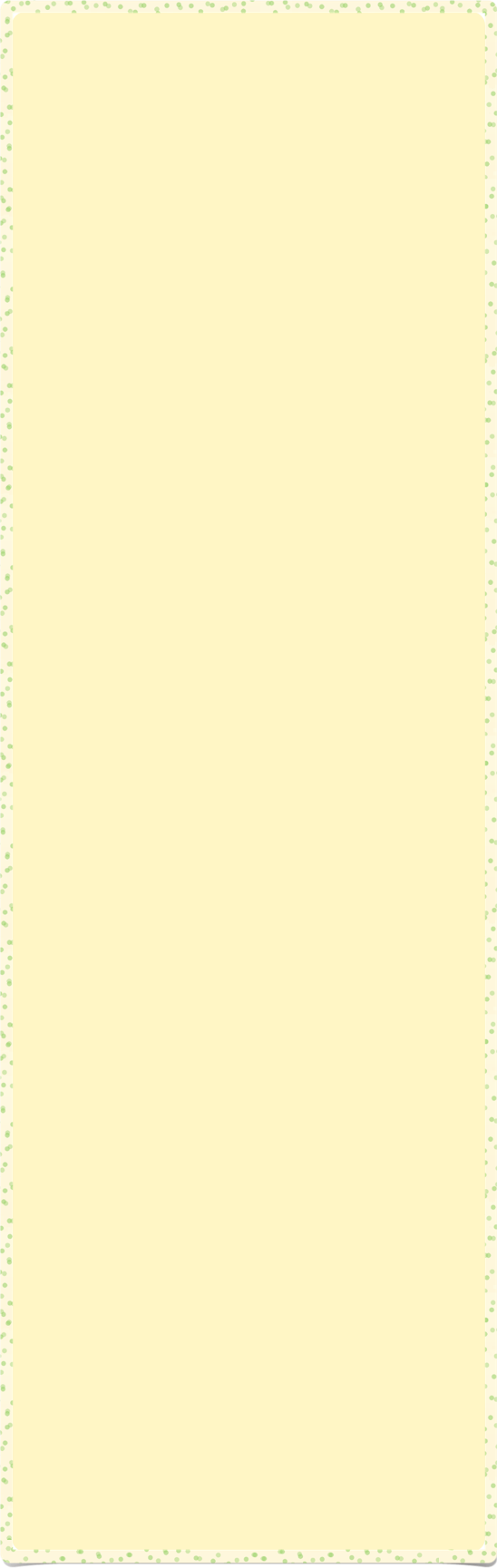

逆流性食道炎
(平成25年12月19日)
逆流性食道炎は明け方に胸が痛み心臓の病気と間違えられることがある。寝ている時食道に胃酸が逆流して炎症を起こしたために起こる胸痛で、心電図に異常のない事と胃カメラの検査で食道が爛れていることで診断される。西洋医学的には胃酸の分泌を抑えて食道粘膜への刺激を少なくする治療が行われ、それなりに効果がある。しかし薬を止めると症状が再び出現するようで、根本的な治療を求めて時々漢方外来に患者さんが来られる。
漢方的な立場で見ると胃酸を抑えることは根本的な治療になっていないように思える。つまり名前が示すように胃液が食道に逆流することが問題で、それを改善することが根本的治療ではないかと考える。本来胃酸は食べた食物の中の細菌を殺すのに必要なもので、健康な人なら適度に分泌されなければならない。消化管の蠕動運動は生理的には口から肛門に向かって食物を運ぶための運動であるが、何らかの理由でスムーズにいかなくなって胃の内容物が胃の中で滞っていて、寝ている時に食道に逆流して症状が起こるのが逆流性食道炎である。従って根本的な治療は食道や胃の蠕動運動を正常に戻し、胃内容物が逆流しないようにすることである。蠕動運動を正常に戻す処方を漢方では理気薬と言う。
蠕動運動がうまくいかないときにどのような症状が起こるか整理してみると、咽頭や食道では咽の詰まりや食道の異物感として自覚され、喉頭食道神経症などの病名がつく。胃液の逆流で痛みが強い時に逆流性食道炎と言われる。また食道の出口つまり胃の入り口を噴門と呼び、そのあたりが痙攣すると食道が詰まって似たような症状が起こり、食道アカラシアという病名がつく。また食道が横隔膜の隙間を通って胃につながるが、食道が通る横隔膜の穴を食道裂孔という。この穴が大きくなって胃が胸部に滑って入りこんでいる状態を食道裂肛ヘルニアという。このときも胃液が食道に逆流しやすくなる。
食道や咽の蠕動がうまくいかない時に使われる代表的な漢方薬が半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)である。其の中に含まれる厚朴、半夏、茯苓、生姜などが蠕動運動を正常に戻す作用がある。
また胃の蠕動運動がうまくいかないときには、胃内容物の排泄がうまくいかないため食後の胃もたれとして自覚される。胃もたれが長く続くほど胃腸の働きが悪く、胃が弱いことになり、四君子湯(しくんしとう)や六君子湯(りっくんしとう)が使われる。其の中には人参・白朮・茯苓・生姜が入っていて胃の排泄をよくするようになっている。同じ様な効果を持つ処方に茯苓飲(ぶくりょういん)がある。
食道と胃の蠕動運動を同時に改善するのに茯苓飲と半夏厚朴湯を併せた茯苓飲合半夏厚朴湯(ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう)という処方があり、逆流性食道炎にはぴったりの処方ではないかと重宝している。
ではなぜ食道や胃の蠕動運動の異常が起こるのだろうか。消化管運動の調整は自律神経によって調整される。則ち活動する時は交感神経によって消化管の動きが抑制され、身体を動かす筋肉に血流やエネルギーを供給し、休息する時に副交感神経の働きで消化管の動きが活発になりエネルギーを蓄えるため、蠕動運動も促進される合理的な仕組みになっている。従って食道や胃の蠕動運動がスムーズでないということは常に交感神経が緊張してリラックスできないことを示している。つまり心理的なストレスが消化管の運動を抑制することになる心身一如の典型例であることが理解される。先にストレスは頚椎の歪みにとして蓄積されると言う仮説を提示したが、過去のストレスによって頚椎が捻じれていることもリラックスできない遠因となり、病態をわかりにくくしているようである。頚椎の捻じれを治すと咽の異物感が即座にとれる事をよく経験しているので、交感神経の緊張に頚椎の捩れが関係している事はほぼ間違いないと考えている。
