いざ行かん 我らの家は五大洲
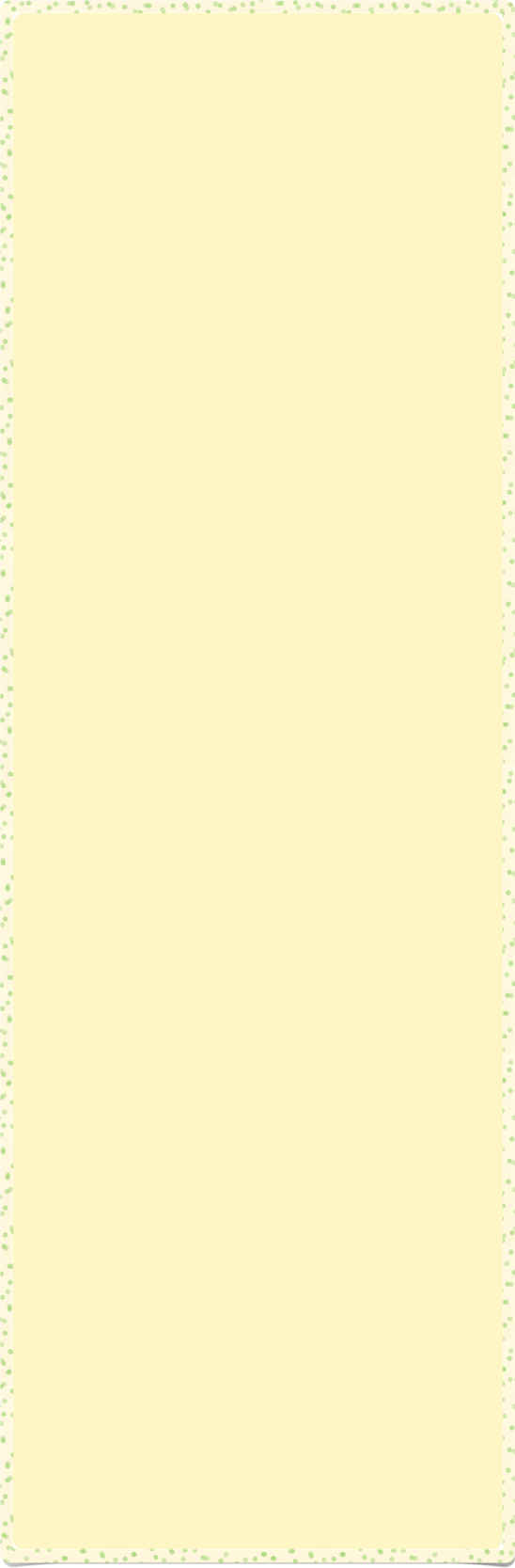

いざ行かん 我らの家は五大洲
(平成25年6月15日)
此れは沖縄の移民の父といわれる当山久三の言葉である。此の言葉と共に思い浮かぶのは、遠く海の彼方を指差して遠くを見つめる久三の彫刻の写真である。当然未来を見つめるので顔を少し上げ、遠くを見つめる姿勢をとる。これから移民の話をするわけではない、未来に向かう時に無意識に我々の採る姿勢の話をしようというのである。
序でにもう一つ、坂本九の『上をむいて歩こう』というヒットソングがある。何故上を向くのかというと、悲しみでこぼれる涙が落ちない様というのであるが、幸せは雲の上にあるので幸せに向うために上を向くというのである。悲しいからうつむくのが自然である。しかし、下を向くと落ち込んでしまう気持ちが増幅されるので、せめて上を向いて気持ちが落ち込まないようにという思いが込められていて、その思いに対する共感がヒットにつながったように思われる。これらのことは、人間は希望に向かい、幸せ目指す時は上を向くという潜在的な意識が普遍的に働く事を示している。したがって前向きに生きるということは顔を上げて遠くを見つめる姿勢になるのである。それが気の型というべきものである。
では逆に下を向くとどうなるのだろうか。上を向くのとは逆の意味が生まれる。下を向くときは恥ずかしくて顔を上げられない、疲れて気持ちが後ろ向きになるとき、何でも悪い方向に考える時、とあまりいいイメージと結びつかない。
何故このような話をするかというと、最近の患者さんを見ていると疲れて希望を失い、不定愁訴に悩んでいる人が多く、その心の状態が体の状態と密接に関係があるのではないかと思いついたからである。
話はこうである。私の外来に不定愁訴の人が多くみえる。その方達は頚椎に問題があり、頚椎の伸展つまり上を向く事が制限されている。過労やストレス、長時間下を向くパソコン業務などで頸椎が捩れ、上を向く事すなわち頚椎の伸展で痛みが起こり、思い切って上を向けないようである。すると上を向かずに下ばかり向く傾向になるので、それによってマイナス思考、後悔、ためらいなど下向きの人生に無意識に導かれるのではないかと思いついた。上を向きにくいうえに、肩こりや頭重などの不快な症状を伴い、いよいよ下にうつむく暗い人生になるのではないかと思われる。
当院ではストレスや疲れは頚椎の捻れや生理的前消失、ストレートネックとなって蓄積されるという、臨床経験に基づく仮説によって、鎖骨調整で積極的に頚椎の捻れを整復し、楽に上が向けるようにしている。すると楽に上が向け、頭や肩も軽くなり、さらに心が軽くなり、前向きに将来の希望に向って頑張ろうという気持ちになる。これはには、上を向く姿勢によって無意識に気持ちが変わる効果もふくまれるのではないかと考える。
このような事をしていると、われわれの感情がそれに伴って自然に導かれる姿勢を作り出しているように見える。そこに民族の普遍性がみられるとき固有の文化として、逆に感情表現の型として無意識あるいは意識的に使われるのではないかと考える。このようにして現象から普遍的な動作の型を導いたのではないかと考えてみるのである。演劇や歌舞伎などで身振り大きくして気持ちを表現する時、無意識の型によって気持ちを表現する事につながってくる。たとえばうつむいたときは憂い悲しみ、恨みにつながるだろうし、喜ぶときは自然に顔をあげるのではないかと考える。
すると医学的には治療に因って体が楽になると姿勢を整えて上を向かせ、人生が明るくなるような積極的な指導も必要になるのではないかと考えるようになった。
